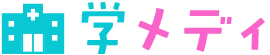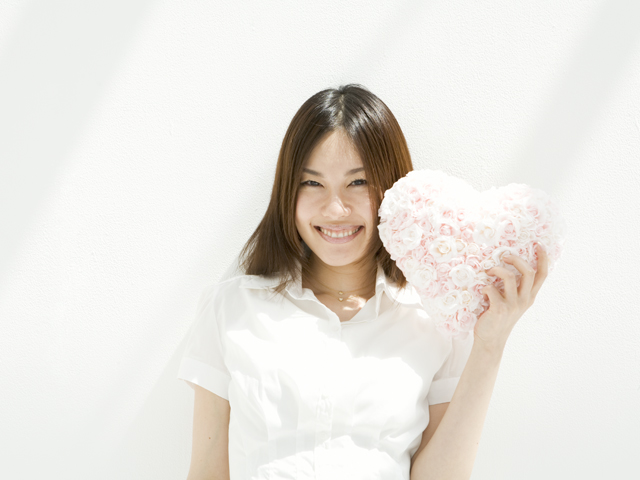胚培養士とは
胚培養士(はいばいようし)は、不妊治療の現場で受精卵を扱う専門職です。
体外受精では、女性の体から取り出した卵子と男性の精子を体外で受精させます。
その受精卵(胚)を母体に戻すまでの間、適切な環境で管理・培養するのが胚培養士の仕事です。
具体的には、精子と卵子を受精させたり、受精卵を培養したり、将来の移植のために胚を凍結保存したりします。
「新しい命の誕生」を支える、とても繊細で責任の重い仕事です。
胚培養士の資格
胚培養士は国家資格ではなく、学会が独自に認定している資格を取ることで名乗れる職種です。
現在は大きく3つの資格があります。
・認定臨床エンブリオロジスト/日本臨床エンブリオロジスト学会
・生殖補助医療胚培養士/日本卵子学会
・生殖補助医療管理胚培養士/日本生殖医学会・日本卵子学会
いずれも実務経験や症例数が求められます。
試験形式は筆記・面接・実技(DVD提出など)。
資格更新は5年ごとです。
臨床検査技師からこの資格を取得する傾向が高かったようですが、生命科学や畜産系出身者などからも受験・取得できます。
胚培養士になるには
胚培養士を目指す人の多くは、生物学系や農学系の大学を卒業しています。特に臨床検査技師の資格を持っていると、医療現場での知識や技術がそのまま活かせるため、有力なルートといえるでしょう。薬学部や看護学部の出身者が培養士として働くケースもあります。「医学部に進まなくても医療に関われる」という点は、学生にとって魅力的なポイントかもしれません。
働く環境とキャリア
胚培養士の主な職場は、不妊治療を専門とするクリニックや病院です。
大規模な施設では数十人規模の培養士チームが存在していることも。
また、培養士は国内外の学会に積極的に参加し、最新技術や研究成果に触れる機会も多くあります。
向いている人の特徴
胚培養士に向いているのは、まず手先が器用であること。
また、培養業務は顕微鏡を使って細かい操作を続けるため、集中力や注意力が求められます。
理系の実験が好きだったり、コツコツと作業に取り組むのが得意な人には特に向いている職業と言えるでしょう。
しかし、何より大切なのは「胚を大切に扱う気持ち」です。
命の始まりを預かる仕事なので、倫理観や責任感が強い人でなければ務まりません。
「命の始まりに関わる仕事がしたい」と考える人にとって、胚培養士は大きなやりがいを感じられる職業です。
体外受精などの生殖補助医療では、医師だけでなく胚培養士など複数の専門職が関わり、工程や用語も多くなりがちです。京都で不妊治療の選択肢を整理し、医療機関を探す際の見比べ方や確認点をまとめたページも併せて参照すると理解が進みます。質問事項を整理する目的でも使えます。個別の相談は医療機関で行ってください。
【外部】京都の不妊治療サイトを見てみる